
「AI受診相談ユビー」とは
こんにちは。
ヘルスケアアプリを紹介する「デジタルヘルスのアプリケーションをひたすら紹介するブログ」です。

AIアプリで自分の病気を調べたい人必見!
111回目の今回は、久し振りにFemtech関連以外のヘルスケアのアプリケーションを紹介させて頂きたいと思います。
お久し振りです!
突然ですが、凄いAIアプリです!これは凄い。
なんと「AI受診相談ユビー」は症状を入力していくと病気を予測してくれるんです!
アプリを立ち上げ、気になる症状・病気についてAIからの質問に答えていくと、症状と関連性の高い病気とその病気についての情報が得られます。
また、地域の適切な医療機関・診療科・救急相談窓口へのご案内してくれます。
私もやってみましたが、とても分かりやすく、すいすい質問が流れていき、数分で自分の症状から推測できる病気の候補が出てきました。
そして、すぐに病院を受診するように!との警告が。
今回は試しでやってみただけですので、受診はしませんが、ちょっと気になる症状がある際に、病院の受診をアドバイスしてくれたらとても助かりますね。
いざというときのために、ダウンロードしておいて損はないヘルスケアアプリです。
そして、本アプリのAIは、なんと!50名を超える様々な専門科の現役医師が監修を行なっており、実際の医療現場でも利用されているものとのことです。
そして、このAI受診相談のテクノロジーを支えるデータもしっかりとエビデンスのあるガイドラインなどを参考に構築されている模様です。
そして、なんと!開始から2年で、累計利用回数は全国約4000万回に達し、月間利用者数が500万人を超えたとのことです!
詳しくはこちら

病気を疑ったり体調不良時に病院やクリニックに行く際に困ること
Ubie社の調査によると、病気を疑ったり体調不良時に病院やクリニックに行く際に困ることで最も多いのは、
- 病院・クリニックに行くべき症状なのかわからない(38.7%)
- どの医療機関・診療科に行けばよいか判断に迷う(38.2%)
- 良い病院・クリニックがなかなか見つからない(22.0%)
となりました。
3人に1人以上の生活者が、医療機関に行くと判断してからの医療機関探しや予約よりも、その手前での医療機関を受診するか否かの判断に困っており、また「ネットで調べるほど、情報が多く混乱する」という状況に陥っているのが現状のようです。

ヘルスケアアプリで医療機関に受診するかどうかを教えてくれたらとても便利ですね。
「ユビー」利用者の声
夫婦で利用し、体調不良時はユビーの検索結果をシェアし合っています
愛知県在住/40代/女性
動悸や息切れなどこれまで経験のない症状が長期間続き不安になり、インターネットで症状を調べていた時にユビーを知りました。その症状がどんな病名と関連しているかを調べることができ、結果、適した診療科を受診する手がかりになりました。夫も利用しており「体調がすぐれない時まずユビーで症状を調べてみる」「体調が悪い時、お互いの検索結果を共有し状況を伝え合う」が我が家では習慣になっています。
鼻の違和感から大学病院で指定難病と診断されました
熊本県在住/40代/女性
既に複数回利用しており、頭の痛みなど自分ではうまく表現できない部分をAIが質問でうまく言語化してくれ、症状をしっかり伝えられていると感じています。ある日、鼻に違和感を覚えユビーを利用した所「すぐ受診を検討したほうがいい」という病名が表示され、かかりつけ医を受診。その後紹介された大学病院で指定難病と診断されました。鼻の違和感は日常生活に大きな支障が出る程ではなかったので、ユビーの情報が受診する後押しになりました。
自治体と地域医療のデジタル活用支援に関する連携協定を締結
2022年6月3日から、広島県三原市(市長:岡田吉弘、以下「三原市」)と地域医療のデジタル活用支援に関する連携協定を締結したとのことです。
(プレスリリースはこちら)
Ubie 株式会社が地方自治体と連携協定を締結するのは、2022年3月1日の千葉県御宿町に次いで、全国で二番目とのことです。

三原市との協定は、デジタルを活用した市民の新しい受診スタイルの提供と持続可能な医療体制の構築を目的とするもので、三原市において症状検索エンジン「ユビー」(https://ubie.app/)と、医師が患者さんの症状を来院前に把握できる「ユビーリンク」を活用した取り組みです。

今回の取り組み内容としては、三原市の公式ホームページ内に「ユビー」紹介ページが掲載されております。
また、2021年3月に開設し約2万人が登録する三原市公式LINEにてユビーに関するお知らせ配信を行い、市民へサービスの活用とそれによる新しい受診スタイルの周知を積極的に促すようです。
そして医療機関側へのサポートとして、かかりつけ医として市民の健康を守るゲートキーパーの役割を担うクリニック・診療所を対象に「ユビーリンク」の説明会を開催し、デジタルを活用した業務効率化ツールの導入を全面支援していくとのことです。
AI(人工知能)をコア技術とするデジタルサービスを活用し,転入者等のかかりつけ医を持たない三原市民にとって,身近な医療機関を適切に受診しやすくなることで,暮らしやすさの向上につなげていくのが狙いのようです。
とても便利で先進的な自治体サービスですね。

AI受診相談ユビーで利用しているデータ
AI受診相談ユビーで利用しているデータは、公知かつ信頼性のある出典元(各種診療ガイドラインや診療指針など)に則っています。
社内外の監修医師によりデータソースを常にアップデート、運用することより、適切な質問を提示し、適切な医療を受けられるサポートをできるように努めています。
実際にどのようなデータが使われているか、一部の例を以下に挙げます。(2020年現在)
- 高血圧治療ガイドライン2019 (日本高血圧学会)
- 熱中症診療ガイドライン2015 (日本救急医学会)
- 関節リウマチ診療ガイドライン 2014 (日本リウマチ学会)
- 造血器腫瘍診療ガイドライン 2018年版(日本血液学会)
- 血管炎症候群の診療ガイドライン(2017年改訂版) (日本循環器学会など)
- 脳卒中治療ガイドライン2015〔追補2019〕 (日本脳卒中学会)
- 肝癌診療ガイドライン(補訂版) 2017年版
- 肛門疾患(痔核痔瘻裂肛)診療ガイドライン 2014年版(日本大腸肛門病学会)
- 産婦人科診療ガイドライン産科編 2020 (日本産科婦人科学会)
- 産婦人科診療ガイドライン婦人科外来編 2020 (日本産科婦人科学会)
- 潰瘍性大腸炎クローン病診断基準治療指針 令和元年度 改訂版(難治性炎症性腸管障害に関する調査研究 (鈴木班))
- 慢性頭痛の診療ガイドライン2013 (日本頭痛学会)
- 急性鼻副鼻腔炎診療ガイドライン 2010年版(日本鼻科学会)
- 急性膵炎診療ガイドライン 2015 (日本腹部救急医学会など)
- 急性腹症診療ガイドライン 2015[第1版第3刷] (日本腹部救急医学会など)
- 急性胆管炎胆嚢炎診療ガイドライン2013[第2版] (日本腹部救急医学会など)
- 急性冠症候群ガイドライン(2018年改訂版) (日本循環器学会)
- 形成外科診療ガイドライン 2015 (日本形成外科学会,日本創傷外科学会,日本頭蓋顎顔面外科学会)
- 女性下部尿路症状診療ガイドライン[第2版] (日本排尿機能学会、日本泌尿器科学会)
- 大腸憩室症ガイドライン 2017(日本消化管学会)
- てんかん診療ガイドライン2018(日本神経学会)
- ギランバレー症候群、フィッシャー症候群診療ガイドライン2013 (日本神経学会)
- アレルギー総合ガイドライン2019 (日本アレルギー学会)
- NASHNAFLDの診療ガイド2010 (日本肝臓学会)
- JRC 蘇生ガイドライン 2015(日本蘇生協議会)
- DSM-5 精神疾患の分類と診断の手引 (日本精神神経学会)
- 「喘息とCOPDのオーバーラップ(Asthma and COPD Overlap: ACO) 診断と治療の手引き2018」(日本呼吸器学会)
- Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China.Engl. J. Med. 2020, 10.1056/NEJMoa2002032.
- Self-reported Olfactory and Taste Disorders in Patients With Severe Acute Respiratory Coronavirus 2 Infection: A Cross-sectional Study.Clin Infect Dis. 2020 Jul 28;71(15):889-890.
- Clinical Characteristics of COVID-19 Patients With Digestive Symptoms in Hubei, China: A Descriptive, Cross-Sectional, Multicenter Study.Am J Gastroenterol. 2020 May;115(5):766-773.
- Alterations in Smell or Taste in Mildly Symptomatic Outpatients With SARS-CoV-2 Infection.JAMA. 2020;323(20):2089-2090.
- WHO “Coronavirus disease (COVID-19)” ((Accessed on June 28, 2021.)
- Clinical characteristics of 345 patients with coronavirus disease 2019 in Japan: a multicenter retrospective study. J Infect. 2020 Nov; 81(5): e3–e5.
- Acute Onset Olfactory/Taste Disorders are Associated with a High ViralBurden in Mild or Asymptomatic SARS-CoV-2.Int J Infect Dis. 2020 Jul 26;S1201-9712(20)30578-6.
それでは医療機関を受診するかどうかを判断するために相談できるヘルスケアアプリ「AI受診相談Ubie」を見ていきましょう!
「AI受診相談ユビー」の主な機能(公式サイトから引用)
「AI受診相談ユビー」は、質問に答えるだけで、参考病名や近所の適切な病院など、「受診の手がかり」がわかるアプリです。
「AI受診相談ユビー」でできること
1. 体調変化の「なぜ」がわかる
- 症状の深刻さとその理由
- 関連する病名とその理由

2. 受診の「どこに」がわかる
- 受診すべき診療科
- 関連する病気が診れる近くの病院

3. 診察時の「何を話せば?」がわかる
- あなたが医師に伝えるべき症状
※あなたの回答結果をユビーが「医師語」に自動翻訳。受診先に事前共有し、伝え漏れを防止できます

「AI受診相談ユビー」ができた背景
〜誰もが、適切なタイミングで、適切な医療を受けられるサポートを〜
「調べれば調べるほど情報があふれて、わからない」
インターネットで情報が簡単に手に入るようになった現在でも、医療についての適切な判断は依然として難しいままです。誰もが、適切なタイミングで、適切な医療を見つけられるようにサポートしたい。その想いから、医師と開発者によって「AI受診相談ユビー」はつくられました。
「AI受診相談ユビー」では、気になる症状についてAIからの質問に答えると、症状と関連性の高い病名とその病気についての情報がわかります。また、近所の適切な医療機関・診療科・救急相談窓口へのご案内も「AI受診相談ユビー」経由で。
「AI受診相談ユビー」のAIは、50人を超える様々な専門科の現役医師が監修し、実際の医療現場でも利用されています。「AI受診相談ユビー」は「適切なタイミングでの適切な医療との出会い」の橋渡しによって、みなさんの健康・安全をサポートし、医療についての不安・悩み・苦痛を和らげます。

サービスの目的と位置付け
入力された情報に基づき、関連する病気やその病気についての情報、関連する医療機関の情報を提供するサービスです。本サービスは、医療機器ではないため情報提供のみを行い、医学的アドバイス、診断、治療、予防などを目的としておりません。
医師や他の医療専門家に代わるものではないため、提供する情報に基づいて医学的判断を下したり、何らかの行動(薬の服用など)を行ったり中止したりしないでください。また、生命を脅かすような状態や緊急の状態では使用しないでください。

「Ubie株式会社」について
会社名:Ubie(ユビー)株式会社
代表:阿部 吉倫 (医師)・久保 恒太 (エンジニア)
所在地:東京都中央区
設立:2017年5月
従業員数:128名 (2021年7月現在)
資本金:20.5億円 (資本準備金含む)
Mission
テクノロジーで人々を適切な医療に案内する
いつでもどこでも情報を得られるようになった今日でも、医療においては適切な情報が患者や医療従事者に行き渡っていません。
早期に発見されていれば救えたかもしれない患者の命を、多くの医療従事者は無念の思いで見届けています。
私たちは、テクノロジーによって世界中の人々を適切な医療に案内します。
そうすることで、健やかに幸せな日々を過ごせる人を増やしていきたいと考えています。

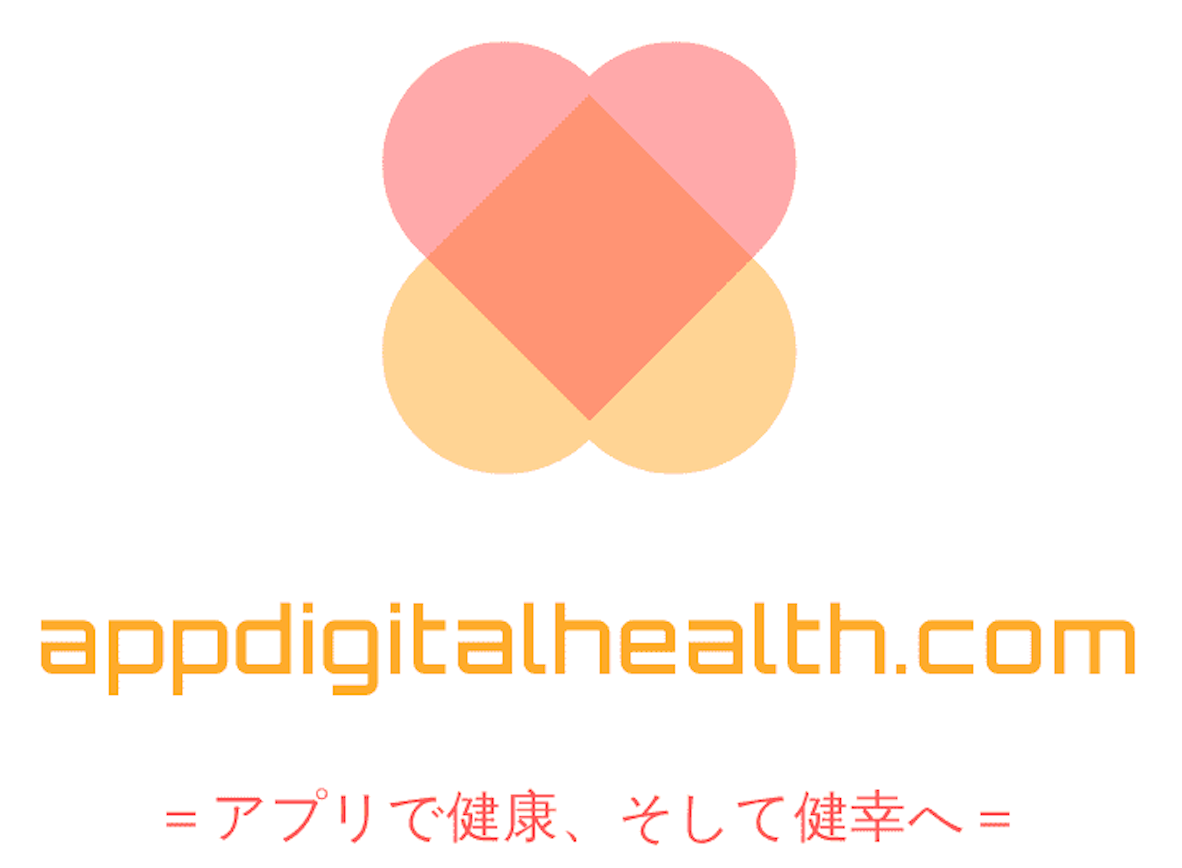





コメント